
先生は、どんなことがきっかけでSDGsや環境問題について考えるようになったのでしょうか?
先週に引き続き、神田外語大学言語メディア教育研究センター長/教授として日々、研究や実践に取り組まれている石井雅章先生にお話を伺っていきます。
前回は、先生のご研究や実践の概要をメインのお話していただきました。詳細は以下のリンクからご確認ください。
今回は、先生の学生時代のエピソードを中心にお話しいただき、その経験や学びがどのような形で、今のお仕事やご研究に繋がっているのかを探っていきます。
お子様の学びの環境づくりという観点でもヒントになる内容が込められていますし、SDGs含め物事について考える上で重要な姿勢・感覚についても言及されていて、非常に読みごたえのある内容になっていること間違いなしです。
ぜひ、最後まで読んでいただければと思います。
それでは、石井先生よろしくお願いいたします。
さて、第2回の最初は石井先生が今の研究に興味を持たれた経緯についてお伺いしてみようと思います。
環境社会学をご専門とされ、現在は「SDGs×教育」についてもご研究をされている先生は、どんなきっかけでこの道を志したのでしょうか。
なぜ、SDGsを教育活動のテーマに選ばれたのですか?エピソードなどがあれば、ぜひ教えてください!
自由帳の裏表紙で「2000年に石油が枯渇する」と書かれていたのを見てからでしょうか。
偶然目にしたコラムが今のご研究の原点というのが非常に面白いですね!
現在、SDGsについてご研究されている先生ですが、環境問題への興味の始まりは偶然目にした自由帳のコラムだったのです。
このお話で興味深いのは、何が子どもの好奇心のきっかけになるかは予測がつかないということでしょう。
自由帳の裏のコラム、何気なく読んだ絵本、両親と一緒に見た映画…何がお子様の好奇心を掻き立てるトリガーになるかは、それぞれに違っていて、答えはありません。
その点で、子どもの学びをサポートする保護者としては、そういった出会いや経験の機会をできるだけ作ってあげることが大切になってきます。
また、たくさんの知識・情報や経験を持っていることは、社会で求められる「創造性」の土台にもなってきます。
環境問題について考えるにあたり、石井先生は「社会学」で学んだアプローチが大いに役立ったと述べています。
学んだことを組み合わせて、新しい価値を生み出していくことが「創造」の1つのあり方であり、その引き出しをできるだけ増やしていくことも非常に大切なのですね。
次に、賢者の先生にいつもお伺いしている学生時代に関する質問をしてみました。
環境社会学をご専門とし、活躍しておられる先生が、どんな学生生活を送っていたのかをお聞きして、そこから学びのヒントを得られればと思います。
先生は、どんな学生時代を過ごされましたか?
普通の学生生活です(笑)
いろいろな学問や考え方を知る中で、自分が興味を持てる社会学に出会えたのですね!
先ほどのSDGs研究を選ばれた理由に関するお話とも重なる部分もありますが、やはり様々な学問や考え方に触れることで「自分」が確立されていくのだと実感します。
高校生までは学校で学ぶカリキュラムが決められているので、受け身的な学びになりがちです。
しかし、大学に入ると突然、何を学ぶのかを自分で選ばなくてはいけなくなり、困惑する学生も多いと言われます。
一番勿体ないのは、大学でもそれまで同様の受け身的な学びを続けてしまうことですが、やはり突然「自発的に学びなさい」と言われても対応できない学生が出てくるのは当たり前なのかもしれません。
そういったギャップに悩まないためにも、子どもたちには自分の興味を持ったものや知的好奇心が湧いたものを積極的に学んでほしいですし、その中で学ぶものを自分で選択するという感覚を早いうちから身につけて欲しいですね。
いろいろな学び、経験、人との出会いが学生時代にあり、その中で「社会学」を深く掘り下げて学ぶようになったということでした。
では、それらが今の研究にどんな影響を与えているのかについてもう少し具体的に伺う中で、学生時代にどんな力や技能、姿勢を養う必要があるのかを探っていきたいと思います。
学生時代の勉強や経験が今のご活動にどのように役立っていますか?
社会学を学んだことで受けた影響はやはり大きいです。
見えるものとその背後にある見えないものをリンクさせて考えることが重要なのですね!
抽象と具体をリンクさせて考えるのは、非常に大切なことです。
例えば、「大学に進学したい」というのは、漠然としており、抽象度が高いビジョンと言えるでしょうか。
少し掘り下げていくと、「どの大学に行きたい」「どの学部に行きたい」「どこにある大学に行きたい」「何を学びたい」といった少し具体度の高い情報が出てきます。
さらに掘り下げていくと、「どんな勉強をすべきか」「どの教科を重点的に学ぶべきか」といった自分がすべきことの領域にまで落とし込んだ具体的な戦略が見えてきます。
抽象度の高い「大学に進学したい」という漠然としたビジョンと、「数学を毎日3時間勉強する」といった具体的な戦略は、一見違うレイヤーにあるように見えますが、確かに繋がっていますよね。
実は私たちの生きている社会でも、表面に見えている具体的な事物の背後には、目に見えない抽象的なシステムが広がっています。
前回の記事で先生が挙げておられたように,スーパーに並んでいる野菜という個々の具体的な事物の背後にも、生産や運送から成る目には見えないシステムが広がっています。
その具象と抽象を行き来しながら考えることで、個々の事例からシステムについて考えたり、逆にシステムから個々の事例について考えたりできるというわけですね。
そういう意味でも、SDGsについて学んだり、考えたりする上で、この感覚は非常に重要と言えるでしょう。
石井先生、ありがとうございました。
今回の先生のお話の中での「学びのヒント」としては以下のことが挙げられると思います。
(1)偶然の出会いが子どもの知的好奇心を掻き立てる!
(2)具象と抽象がリンクしているという感覚を持とう!
お子様がどんなものに興味を示すか、どんなことに疑問を示すかは、大人の感性とは違っていて、なかなか想像がつきません。
石井先生は自由帳の裏表紙に掲載されていたコラムが環境問題に寄与したいと考えるきっかけになったそうですが、このように深い思索や探求の入り口は、思いがけない偶然だったりするものです。
アイザック・ニュートンがリンゴが木から落ちるのを見て、「リンゴに対して働いている力が、月や惑星に対しても同様に働いているのではないか?」と考えたという寓話は有名です。

保護者の皆さまとしては、お子様が自ら興味を持って取り組めるような物事に出会えるようサポートしてあげることも大切です。
その中で、お子様に自分で学びたいことを選ぶという感覚も身についていくのではないでしょうか。
また、SDGsについて学んだり、考えたりする上では、具象と抽象を行き来しながら考える感覚を磨いていくことが大切になってきます。
日頃から、表面に現れている具体的な物事の背後にはどんな「目に見えない」世界やシステムが広がっているのかを想像してみましょう。
次回は、SDGsを学ぶ上でどんな力が重要なのか、またどんな教材や本がおすすめなのかといったトピックに踏み込んでいきます。
今回の記事に関連したおすすめの参考書・問題集をご紹介させていただきます。
百人一首新事典
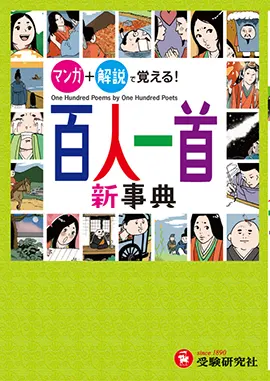 ○各短歌の作者の紹介,短歌の意味,短歌の解説,短歌に出てくる語句の解説,出典(どの和歌集から選ばれたか)などをまとめています。
○各短歌の作者の紹介,短歌の意味,短歌の解説,短歌に出てくる語句の解説,出典(どの和歌集から選ばれたか)などをまとめています。
○「小倉百人一首」に関するコラムや,短歌に出てくる地名などを地図で示したページを設けています。
百人一首というのは、飛鳥時代から鎌倉時代に詠まれた100の名歌を集めた歌集です。
非常に興味深いのは、その1つ1つの歌に、当時の社会状況、経済状況、文化、恋愛、宗教など様々な背景が見え隠れしていることです。
「見えるもの」と「見えないもの(その背後にあるもの)」のリンクを考える上で、百人一首に含まれる歌を1つ1つ、その背景まで掘り下げながら勉強してみるというのは、1つ面白いアプローチかもしれませんよ。